
離婚裁判などで
養育費や婚姻費用の金額を決めるときに利用されている算定表ですが、
社会情勢の変化やシングルマザーの貧困などの社会問題を考慮して、
日本弁護士連合会より2019年12月23日に新算定表が改正されます。
新算定表を用いれば、
もらえる養育費や婚姻費用が1.5倍に増額するそうです。
しかし現状としてこの新算定表がどの程度適用されているのか、
実際に利用できるのか気になるところですよね。
今回は別居や離婚に欠かせない、
養育費や婚姻費用の金額を決める際に利用されている養育費・
婚姻費用算定表改正について詳しく解説します!
これから離婚しようと考えている方は、
ぜひ参考にしてくださいね!
養育費・婚姻費用算定表とは?
養育費は離婚後
子どもを育てるために必要なお金です。
子どもを養育していない方の親が、
子どもを養育しているもう片方の親に対して支払うお金です。
婚姻費用とは、夫婦が別居する際、
専業主婦やパートなどで収入の少ない妻が、
収入の多い夫から生活費をもらうことができます。
例え夫が
「そんな金絶対払いたくねーや!」と言っていたとしても、
調停を申し立てればもらえます。
調停で決まったにも関わらず、
それでも支払わない場合は
強制執行や財産差し押さえすることもできるんです。
子どものためにも離婚後の生活のためにも、
養育費や婚姻費用は必ず請求するようにしましょう!

モラハラ夫と別居中も生活費を確保する方法!婚姻費用ってなに?
養育費・婚姻費用算定表とは、
離婚後の子どもの養育費や、
別居の際に妻と子どもの生活費を支える婚姻費用を決めるとき、
夫婦で金額の合意を得られないときなどに、
金額を決めるときの目安のひとつとして使われるものです。
夫と妻の収入や子どもの人数、
年齢などを考慮して、
おおよその相場を算出します。
こちらはあくまで離婚裁判になったときの目安で、
協議や調停などで
夫婦の合意が得られれば相場以上の養育費や
婚姻費用を得ることも可能です。

モラハラ夫と離婚するなら裁判しかない?離婚の種類と裁判について徹底解説
ただ弁護士をはさんだ場合、
調停であっても算定表に基づいた金額を
提示するケースが多いようです。
私も弁護士に相談に行ったときは、
この算定表を基準に請求するようにいわれました。
このように弁護士が入った場合たとえ裁判にならなくても、
養育費や婚姻費用の金額を決めるときには
重要な指針になっているのがこの算定表なんです。

算定表見直しでもらえる養育費や婚姻費用はどう変わる?
そもそも現在の算定表は2003年に作られたものなんです。
15年前ですからねー
古いですよね。
そこで日弁連が
「時代と合っていない」
「金額が低すぎてシングルマザーの貧困を招いている」
「義務者と子どもの生活水準に格差がありすぎる」として、
計算方法を見直して適正な金額を出していこうということです。
養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言/日本弁護士連合会
日弁連のHPを見ると、
難しいこといっぱい書いてますが、簡単にいうと
「もう少し養育費や婚姻費用上げてこーよー!」
ってことみたいです!
今シングルマザーの貧困が社会問題になっていますよね。
厚生労働省が公表している
平成28年度の全国ひとり親世帯等調査結果報告では、
養育費の平均は3~4万程度です。
とてもじゃないけど、
子どもを養育できる金額じゃないよねー!!
しかも実質養育費をきちんと受け取っているのは、
シングルマザーのたった2割だけなのが現状です。
多くのシングルマザーは
「夫と今後関わるのがイヤ」
「さっさと離婚したかったから」
という理由で養育費の取り決めをしていないようです。
子どもが小さいとなかなかフルタイムで働くことができず、
パートを掛け持ちしてもなかなか貧困から抜け出せない家庭が多く、
シングルマザーの貧困は根強い問題にもなっています。
しかし養育費は子どもが健全に育つために必要なお金です。
お金のことが不安で離婚できず、
せめて子どもが成人するまではと我慢して
結婚生活に耐えている女性が非常に多いように、
これから離婚したいと考えている人にしたら、
お金のことは切っても切れない問題ですよね。
これから離婚を考えている女性には、
今回の養育費・婚姻費用算定表改正はありがたい動きですね!
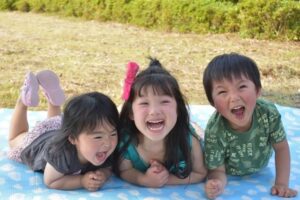
新算定表と現算定表の違い
これまでの現算定表では、
夫の収入妻の収入、子どもの人数、
年齢などを考慮して養育費や婚姻費用が決められていました。
これまでは義務者(養育費や婚姻費用を支払う側)の
総収入に対しておおよそ4割程度の養育費に対し、
新算定表では義務者の総収入に対して
6~7割程度に増えるようです。
また現算定表では子どもの年齢は
0~14歳、15歳~19歳に分けられ、
金額にも幅がありましたが、
新算定表では子どもの年齢は
0~5歳、6~14歳、7~19歳と
より細かく分かれるようになり、
金額も幅をなくしてきちんと決定されるようになりました。
例えば
・新算定表:7万
かなり高額になりますね!
・現算定表:8~10万
・新算定表:15万
このようにもらえる金額が
だいたい5万くらい増えています。
1ヶ月5万も増えるのは、
もらう側としても払う側としてもかなり大きいですね。
これは支払う側と
子どもの生活基準をある程度合わせる目的があります。
月に5万増えれば、
これまであきらめていた習い事を始めたり、
我慢させていた欲しがっていたものを買ってあげることもできますね。
【追記】2020.6.25
実際に調停や裁判所では
新算定表は適用されていませんでした。
裁判になればおそらく
裁判所のHPで掲載されている算定表が使われるかと思います。
裁判所の算定表も新しくなったとの記載はありますが、
弁護士会が提示している算定表よりはかなり低い印象です。
裁判所は新算定表を考慮していない?
ほとんどの裁判所では新算定表は採用されておらず、
裁判所のホームぺージでも算定表は現算定表のままです。
しかし今回裁判所のホームページを確認すると、
12月23日から新算定表が掲載されるそうなので、
離婚裁判においても新算定表が使用される可能性が高いですね。
ただ新算定表の金額は、
現算定表の金額の1.5倍になることから
「こんなに高額になっては義務者が支払い続けるのは難しいのでは?」
と懸念されています。
せっかく時代の流れに合わせた新算定表ができたというのに、
採用されなければ意味がありませんよね。
離婚で損しないコツ!
現在のところ裁判所などではまだ新算定表は浸透されていないので、
養育費や婚姻費用の取り決めをするときには、
義務者側の弁護士は現算定表の金額を基準に言ってくる可能性が高いです。
裁判になれば
今の時点では現算定表の金額に決まる可能性が高いと思います。
ただしそれは裁判になったときだけです。
たとえ相手側に弁護士がいたとしても、
協議や調停で夫の合意が得られれば新算定表の金額は
もちろんそれ以上の金額の養育費をもらうことも可能です。

まとめ
社会の変化や母子家庭の貧困などの
問題点を考慮してできた新養育費・婚姻費用算定表。
しかし実際に裁判所などが利用しているケースは少なく、
まだまだ浸透しているとはいえません。
算定表通りなら現算定表の金額以上をもらうのは非常に難しいですが、
協議離婚や調停なら夫の合意さえ得られれば
新算定表に基づいた金額や
それ以上の金額を請求し受け取ることも可能です。
女性がひとりで子どもを育てて生きていくのは
並大抵ではありません。
子どもと夫を会わせたくないから、
夫ともう二度と関わり合いたくないから、
どうせ夫が払ってくれるわけないから。
こんな理由で養育費を請求しない女性はとても多いです。
しかし養育費はあなたのためのお金ではなく、
子どものためのお金です。
子どもがさみしい思いをしないように、
不憫な思いをしないように、
我慢することのないように。
必ず子どものために養育費の取り決めはしておいてくださいね!


