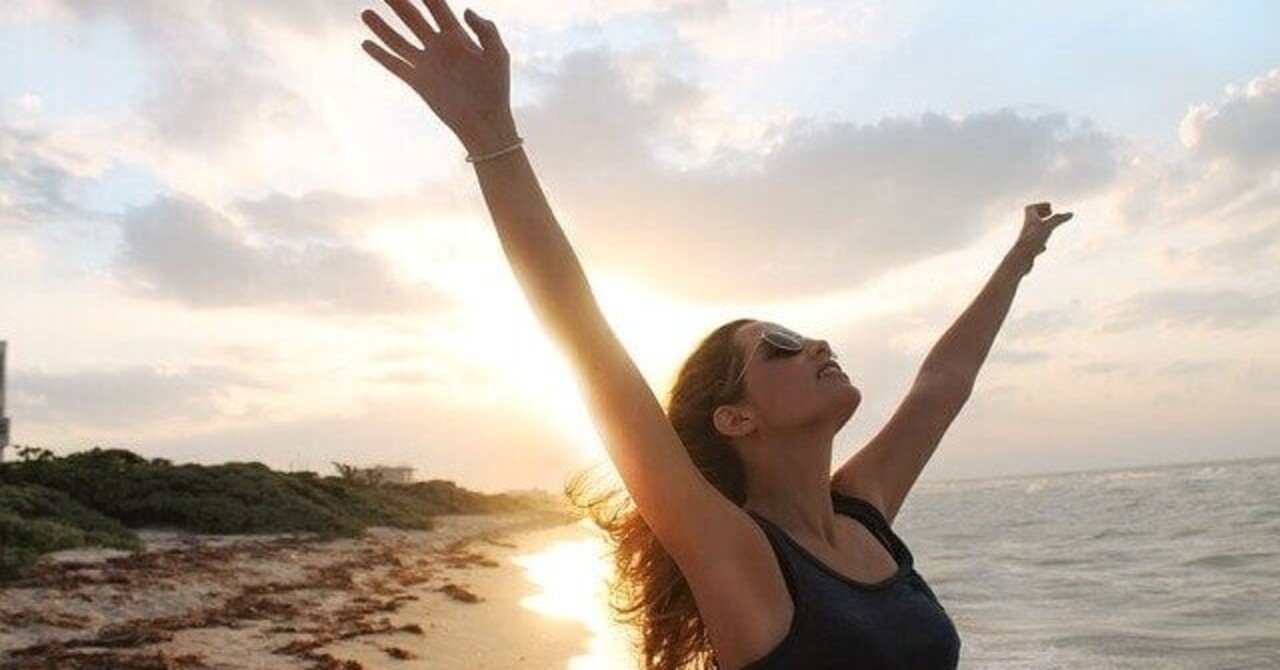離婚や別居を考えているシングルマザーにとって、住まいの選択はとても大きな問題ですよね。
「実家に戻った方が安心かな……」
「でも、親と一緒に暮らすのは気をつかいそう……」
「自分で賃貸を借りるにはお金が心配……」
こんなふうに、迷いながら夜を過ごしている方も多いのではないでしょうか。
実際、私自身も別居後は実家に戻り、そこから1年後に賃貸に引っ越して子どもと3人の生活を始めました。
両方を経験してみて、やっとわかった「現実と気持ちのギャップ」があります。
この記事では、
- 実家暮らしのメリットとデメリット
- 賃貸暮らしのメリットとデメリット
- 最終的にどうやって決めたらよいか
を、実体験も交えて、リアルな視点でわかりやすくご紹介します。
実家暮らしのメリット・デメリット
実家に頼ることで得られる安心と、意外な落とし穴とは?
実家暮らしのメリット
1.経済的な安心感が圧倒的
実家に戻る最大のメリットは、やはり家計の負担が大幅に軽くなることです。
家賃や光熱費がかからない、あるいは最小限に抑えられることで、生活の見通しが立ちやすくなります。
特に、まだ収入が安定しないシングルマザーにとって、これは大きな支えとなります。
- 家賃(平均5万~7万円前後)
- 水道光熱費(1万~1.5万円程度)
- 食費(日常的にシェアすることで圧縮可能)
- 車の維持費(親の車を借りられるケースも)
また、固定費が少ない分、将来に備えて貯金を増やすことも可能です。
2.子どもの心のケアがしやすい
離婚や別居直後は、子どもにとっても大きなストレスです。
父親と離れる、転校する、新しい環境に馴染まなければいけない…。
そんな中で、実家に戻ればおじいちゃん・おばあちゃんの存在が子どもの心の支えになります。
- 母親が仕事で帰宅が遅れても、子どもがひとりにならない
- 食事やお風呂などの「安心できる日常」が維持される
- 感情的にぶつかっても「逃げ場」がある
家族が複数いるというだけで、子どもにとっても「自分はひとりじゃない」という感覚が育まれやすいのです。
3.家事・育児の「孤軍奮闘」から解放される
シングルマザーにとって、「大人がもう一人いることの安心感」は想像以上です。
特に体調を崩したとき、子どもの病気のときなどは、本当に助かります。
- 下の子がお昼寝中に、上の子のお迎えが必要な時
- 自分が発熱・頭痛などで動けない時
- 夜間に緊急の用事ができた時
一人暮らしだとすべてのタスクを自分でこなす必要がありますが、実家だと分担や頼ることができる環境があります。
実家暮らしのデメリット
1.手当や支援の受給に不利になることも
意外と見落としがちなのが、「世帯収入の合算」という制度上の仕組みです。
たとえば、児童扶養手当や保育料の軽減は、あなた自身の収入だけでなく、実家の親の収入も含めて判定されることがあります。
| 支援制度 | 実家暮らしで影響する可能性 |
|---|---|
| 児童扶養手当 | 支給額が減額または対象外になる |
| 保育料 | 世帯合算で高くなる可能性あり |
| 住宅手当・家賃補助 | 支給対象から外れる場合も |
つまり、収入が少ないにもかかわらず、「支援が受けられない」というジレンマが起きることも。
2. 同居による「見えないストレス」
経済的には助かっても、親との価値観の違い、生活スタイルのズレが大きなストレスになることも少なくありません。
私自身も経験しましたが、
- 家事の分担が偏ってしまう
- 育児や家事への口出しが多い
- 自由が利かず、気が休まらない
ということが重なり、「ありがたいはずなのに、つらい」という矛盾を抱えていました。
家事協力が思うように得られなかったり、子育ての方法に口を出されたりすると、毎日の生活にじわじわとストレスが溜まっていきます。
賃貸暮らしのメリットデメリット
精神的な自立と自由を手に入れたいなら?暮らしのリアルを見極めよう!
賃貸暮らしのメリット
自分のペースで暮らせる「自由と解放感」
賃貸での一人(子どもとの)暮らしの魅力は、なんといっても「自分の暮らしを、自分のリズムでコントロールできる」こと。
実家では家族の目や口出しがストレスになっていた方も、賃貸に移ることでそれらから解放されます。
- 食事のメニューも自分と子どもの好みで決められる
- 家事のタイミングや方法も自分のルールでOK
- 手抜きしたって、誰にも文句を言われない
日々の小さな選択を他人に左右されずに済むことで、「ようやく自分の家になった」という実感が得られます。
手当や支援が受けやすくなる
賃貸での暮らしは、世帯が分かれることで行政支援が受けやすくなるという面もあります。
| 支援制度 | 期待できるメリット |
|---|---|
| 児童扶養手当 | 実家の収入と合算されないので対象になりやすい |
| 保育料 | 自分の収入だけで算定されるため軽減されやすい |
| 家賃補助・公営住宅 | 条件が合えば支援を受けられることもある |
行政からの経済的支援をフル活用したい方には、別世帯の賃貸暮らしが有利に働く可能性が高いのです。
3. 「親離れ・子離れ」のバランスを保てる
親との関係が良好であっても、ある程度の距離感があった方がお互いにストレスを感じにくくなることがあります。
実家にいると何かと頼りたくなったり、逆に親からの干渉が増えてしまったり…。
適度な距離を保てることで、「いざという時は頼れる」「でも普段は自立している」という安心感と成長のバランスがとれます。
私自身も、実家を出た今は、親との距離感がちょうどよく感じています。
賃貸暮らしのデメリット
経済的な負担は確実に増える
最大の壁はやはり「お金」です。
家賃、水道光熱費、食費、交通費、保険、車両費……すべてをひとりの収入で賄うプレッシャーは大きくのしかかってきます。
- 家賃:5万~7万円
- 光熱費+通信費:約1.5万円
- 食費:3万~4万円
- 車維持費:1.5万~2万円
私自身、実家にいた頃の生活費に比べ、「3倍以上に増えた」と感じます。
2. すべてを「ひとりで抱える」精神的な孤独
実家では当たり前にいた“誰か”がいない。
これは予想以上に大きなストレスとなります。
- 子どもの急な体調不良でどうしていいかわからない
- 家電が壊れてパニックになる
- ちょっとした愚痴や喜びを聞いてほしいのに誰にも話せない
こうした「ちょっと困った」ことが重なると、孤独感や責任の重さに押しつぶされそうになる瞬間があります。
たとえ実際に解決しなくても、「近くに頼れる人がいる」ことの安心感は、生活の安定には欠かせません。
特に私は自宅でひとりで仕事をしているので、「わざわざ電話するほどじゃないけどちょっといいことがあって聞いてほしい」なんて思うことも多いです。
結局、実家と賃貸どちらがいいの?
正解は「状況と心のバランス」で決まる
実家と賃貸、どちらにもメリットとデメリットがあります。
大切なのは、あなた自身とお子さんの心身にとってどちらがより健やかに過ごせるかを見極めることです。
たとえば……
| チェックポイント | 実家がおすすめのケース | 賃貸がおすすめのケース |
|---|---|---|
| 経済的な安定性 | 収入が不安定、貯金がまだない | 安定収入がある、手当が見込める |
| 子どもの年齢 | 小さくて目が離せない | 思春期以上、プライバシーが必要 |
| 親との関係性 | 良好で協力的 | 口出しや干渉がストレスになる |
| 支援制度の条件 | 親と同居でも手当が受け取れる | 世帯分離で支援を活用したい |
| 精神的な負担 | ひとりでは不安・疲弊しがち | 自分の空間と自由がほしい |
選ぶ際は、「今だけ」ではなく、半年後・1年後・3年後を見据えて考えることも大切です。
一時的に実家に頼り、心と経済を整えてから自立を目指すのも立派な選択。
反対に、多少無理をしても自分のリズムで生活する方が、精神的に安定する場合もあります。
私自身も、今は賃貸暮らしでの大変さを実感しつつ、「それでも、自分の生活に自分で責任を持つことの充実感」を感じています。
まとめ|あなたの「今」にちょうどいい暮らしを選ぼう
シングルマザーとしての暮らしは、経済的な不安、子育ての責任、そして心の負担…
あらゆる重圧が一気にのしかかります。
「実家に住むのがいいのか」
「それとも、賃貸で自立すべきか」
この問いに「絶対の正解」はありません。
大事なのは、今のあなたとお子さんにとってベストな選択をすること。
選べる状況にあるなら、それはとても恵まれたことです。
そして、どちらを選んでも間違いではありません。
必要があれば途中で選択を変えてもいいんです。
一度決めた選択に縛られすぎず、「柔軟に、でも確実に前に進む」ことを大切にしてください。
そして何よりも、あなた自身を責めたり、追い込んだりしないでくださいね。
頑張っているあなたは、もうすでに立派に“お母さん”として歩いています。